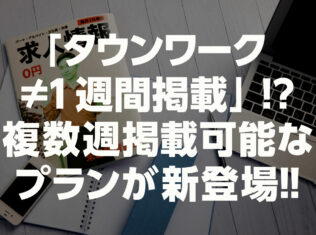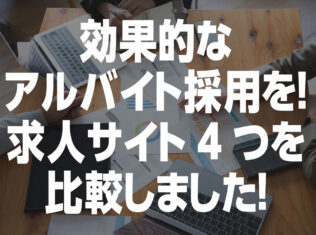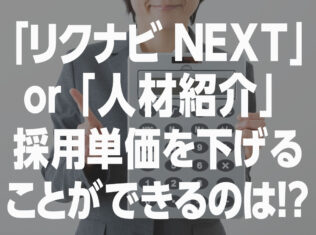目次
はじめに:SNS採用が注目される理由
総務省の調査によると、10〜20代はSNSの利用時間が他の世代よりも長く、情報収集の主な手段になっています。
近年、企業の採用活動においてSNSの活用が注目を集めています。特に、1990年代後半から2010年代序盤に生まれた「Z世代」は、生まれた時からデジタル環境に親しんできた世代であり、SNSを日常的な情報収集やコミュニケーションの手段として活用しています。
従来の求人広告や会社説明会では、企業の実際の雰囲気や社員の人柄を十分に伝えることが難しく、求職者とのミスマッチが生じることもありました。しかし、SNSを活用することで、企業の日常や文化をリアルタイムで発信し、求職者との距離を縮めることが可能となります。
求人広告や説明会では、企業の雰囲気やリアルな働き方が伝わりづらい。
ビジュアルや動画で、リアルな社風を直感的に伝えられる。
実際に、株式会社アド・イーグルでは、SNSを活用した採用活動に取り組んでいます。同社は、バズや拡散を目的とせず、一貫したテーマで自社の等身大の姿を定期的に発信し、企業への理解を深めることを目的としています。
Instagram:【公式】(株)アド・イーグル♡日常
▶コンテンツ:YouTube撮影の裏側・ファッションチェック・社員インタビュー
YouTube:アド・イーグルホールディングス公式youtube
▶コンテンツ会社の雰囲気や仕事のイメージを動画で公開中
Tik Tok:@_adeagle 株式会社アド・イーグル
これらの取り組みにより、採用率や定着率が劇的に改善しました。SNSを活用した採用活動は、Z世代をはじめとする若年層へのアプローチにおいて非常に効果的であり、企業と求職者の相互理解を深め、より良いマッチングを実現する手法として広がりを見せています。
SNS採用とは?メリット・デメリットを整理
Instagram・X(旧Twitter)・TikTok・YouTube・LINEなどのSNSを活用して行う採用活動のこと。
リアルな企業の姿を“自社発信”で伝えられるのが最大の特徴です。
SNS採用とは、企業がInstagramやTwitter、TikTok、YouTube、LINEなどのソーシャルメディアを活用し、求職者と接点を持ちながら採用活動を行う手法です。単なる広報ではなく、リアルタイムな情報発信や双方向のコミュニケーションを通じて、企業の魅力や価値観を伝えることができます。
Z世代の多くはSNSで企業を“検索”。
写真や動画で直感的に魅力を感じてもらえる。
広告では伝えきれない「人柄」「社風」「雰囲気」を
自社視点で発信できる。
従来の求人広告では伝えきれなかった「企業のリアルな雰囲気」や「働く人の人柄」が、SNSを通じて可視化されることで、特にZ世代をはじめとする若年層への効果的なアプローチが可能になります。
・不適切な投稿や対応で企業イメージを損なうリスク
・運用には時間・人員などリソース確保が必要
・フォロワーが増えるまで成果が見えにくい
次のセクションでは、SNS採用のメリットとデメリットを項目別に整理し、導入を検討する企業様にとっての判断材料としてお役立ていただけるように詳しく解説していきます。
採用コストの削減と広範なリーチ
・SNSアカウントは無料で開設・運用が可能
・有料広告も1日数百円からスタートできる
・中小企業でもスモールスタートがしやすい
・フォロワー以外にもシェアで拡散
・求人メディアでは届かない層にも訴求
・企業認知の向上にもつながる
SNS採用の大きなメリットのひとつが、採用コストを抑えられることです。従来の求人広告媒体では掲載費用や手数料が発生しますが、SNSは無料で投稿・運用が可能です。有料広告を活用する場合でも、予算に応じた柔軟な運用ができるため、中小企業でも始めやすいのが特徴です。
また、SNSはその拡散力により、フォロワーだけでなくシェアやリツイートを通じて、多くの潜在的求職者にリーチすることができます。これにより、自社サイトや求人メディアでは接点を持てなかった層にも、企業の存在や魅力を届けることが可能になります。
📊 Z世代の情報収集の起点は「SNS」
検索エンジンではなく、SNSから企業を知る若年層が増加中。SNS上での発信が、採用ブランディングの第一歩に。
特にZ世代は、検索エンジンではなくSNSから情報収集を行う傾向があるため、SNS上での発信は彼らへの接触手段として非常に有効です。広報と採用を同時に叶えるツールとして、SNSの導入は費用対効果の高い戦略といえるでしょう。
まずはSNS採用の基本から着手することで、自社に合った求職者層との接点を広げることができます。
企業文化の発信とブランディング効果
✔ 社風・価値観
✔ 働く人の雰囲気や関係性
✔ 普段のオフィスやイベントの様子
SNS採用の大きな利点のひとつが、自社の企業文化を自然なかたちで伝えられる点です。社風や職場の雰囲気、社員同士の関係性といった「働くリアルな姿」を継続的に発信することで、求職者の理解と共感を得ることができます。
「自分に合う会社か?」が重要視される時代。
共感ベースの採用にSNSは最適です。
定期的な発信は、求職者以外にも良い印象を形成。
「雰囲気が良さそう」といった声が広がります。
とくにZ世代は、給与や条件以上に「自分に合った職場かどうか」「価値観がフィットするか」を重視して企業を選ぶ傾向があります。SNS上でのオープンな情報発信は、こうした層への信頼獲得につながります。
また、採用活動を超えて、企業全体のブランディングにもつながる点も重要です。日常的な発信を通じて、社外にも自社のイメージが広がり、「あの会社って面白そう」「なんか雰囲気いいよね」といった印象形成に貢献します。
📣 採用効率+企業認知の向上
SNSを通じた企業文化の発信は、求職者だけでなく顧客・取引先・地域社会にも好影響を与える「攻めのブランディング戦略」です。
注意点・運用リスク
投稿内容や対応次第で、企業イメージを大きく損なうことがあります。
「社内チェックフローの整備」「投稿ルールの策定」が必須です。
SNS採用には多くのメリットがある一方で、注意すべきリスクも存在します。中でも代表的なのが「炎上リスク」です。投稿内容やコメントへの対応が不適切だった場合、SNS上で企業イメージを損なう可能性があります。
担当者任せにすると投稿が止まるリスクも。
モチベーション維持や社内巻き込みが重要。
フォロワーが増えてもすぐに応募に直結するとは限りません。
ブランディングとして捉え、中長期で継続を。
また、投稿を継続するには一定のリソースが必要です。「担当者任せで更新が止まる」「反応が少なくモチベーションが下がる」といった課題が起こりがちで、社内での体制づくりやスケジュール管理が欠かせません。
さらに、SNS採用は短期的な効果が見えにくいため、「すぐに応募が来る」「フォロワーが増えれば応募につながる」という期待だけではうまくいきません。あくまで中長期的なブランディング活動として捉え、地道に積み上げていくことが成果につながります。
📘 運用ルールの整備が鍵
・目的とターゲットを明確にする
・投稿トーンや返信ルールをガイドライン化
・複数名体制で「止まらない仕組み」を作る
代表的なSNS別|成功事例と特徴
各SNSの特性を理解して、ターゲットに合わせた発信を行うことが採用成功の分かれ道になります。
SNS採用に取り組む企業が増える中、使用するプラットフォームによってアプローチ方法や効果は大きく異なります。ここでは代表的なSNS6種について、それぞれの特徴と成功事例の傾向を整理します。
感覚的に「雰囲気」「人柄」を伝えられる。
若年層の共感を得やすい。
長尺動画で“働くリアル”を丁寧に伝えられる。
社会人経験層や保護者世代への信頼形成にも◎
即時性・通知性に強い。
イベント告知や面接リマインドなど運用性に優れる。
それぞれのSNSには強みと活用ノウハウがあるため、自社の採用ターゲットや目的に応じて使い分けることが成功の鍵となります。次のセクションでは、SNS別に特徴と成功事例を紹介していきます。
SNS採用、もっと知りたい・始めたいとお考えですか?
貴社のターゲットに合ったSNS活用法をご提案します。
「まずは情報収集から…」という方もお気軽にご相談ください。
Instagram:視覚で伝える職場の雰囲気
・画像・動画で企業の“今”をビジュアル発信
・社員紹介やオフィス風景なども高相性
・ストーリーズやハイライトで日常をリアルに伝えられる
Instagramは、視覚に訴える投稿が主軸となるSNSで、企業の“雰囲気”や“空気感”を伝えるのに非常に適しています。職場の内装や社員同士の交流、業務中の様子などを写真や短尺動画で伝えることで、働くイメージを直感的に届けることが可能です。
特にZ世代は、「どんな人と働くのか」「雰囲気が自分に合うか」を重視する傾向があり、Instagramの発信内容は共感・安心材料として機能します。
✅ 活用事例:株式会社アド・イーグル
Instagram(@adeagle_nichizyo_)では、
・YouTubeの裏側
・ファッションチェック
・社員インタビューなどの“日常”を発信中!
こうした投稿を継続的に行うことで、「共感して応募したい」「ここで働いてみたい」という声が増え、実際に採用率や定着率の向上にもつながっています。Instagramは、感覚的なマッチングを重視する層へのアプローチとして非常に効果的なツールです。
Twitter:即時性と双方向コミュニケーション
・「今伝えたい」をすぐに発信できるリアルタイム性
・リプライや引用RTで求職者と直接会話ができる
・拡散力が高く、タイムリーな情報が届きやすい
Twitter(現X)は、リアルタイム性に優れたSNSであり、採用活動において「今伝えたい情報」を瞬時に発信できるのが最大の強みです。採用イベントの告知や、説明会の当日リマインド、新しい募集開始のお知らせなど、スピード感のある情報発信が可能です。
・気軽なリプライで応募者との距離を縮める
・引用リツイートでのリアクションが信頼につながる
また、リプライ機能や引用リツイートを活用することで、求職者との双方向コミュニケーションを実現できます。企業アカウントが気軽に応募者の質問に返信するスタイルは、堅苦しさを感じさせず、親近感を持たれやすくなります。
さらに、企業アカウントの“中の人”が日常的に投稿することで、社員の人柄や会社の温度感が伝わり、共感や信頼の醸成につながります。実際、採用アカウントを中心に“拡散力”を活かしてPV数や応募数が増加した事例も見られます。
✅ おすすめ活用法
・採用イベントや選考進行の「告知」
・親しみやすい日常投稿で「企業の素顔」を発信
・質問受付や回答を通じた「距離の近さ」づくり
Twitterは、スピード感を活かした告知や、フレンドリーな発信で応募のハードルを下げたい企業に向いているSNSです。
Facebook:信頼感のある発信とグループ活用
・30~50代の利用者が多いSNS
・ビジネス向けの投稿に強く、企業の正式情報の発信に適している
・文字量制限が少なく、理念や想いを丁寧に伝えられる
Facebookは、ビジネスパーソンや30〜50代のユーザー層に強いSNSであり、信頼性の高い情報発信ができる点が特徴です。企業としての正式な情報を届けやすく、社風や実績、社会貢献活動などのブランディング要素を丁寧に伝えたい場面に適しています。
投稿には長文も使えるため、企業理念や社員インタビュー、育成方針といった内容もじっくりと伝えられます。応募を検討する層が家族や周囲と相談する際にも、Facebook上の情報は信頼材料になりやすいという利点があります。
・説明会参加者グループで事前情報を共有
・内定者向けの限定コミュニティとして活用
・クローズドな場でフォローアップ・質問受付
さらに、Facebookグループを活用することで、説明会参加者や内定者といった限定的なターゲットに向けたクローズドな情報共有も可能です。これにより、フォローアップや事前情報提供を行う場としても活用できます。
✅ おすすめ企業タイプ
・中堅~ベテラン層への訴求をしたい
・企業の信頼性・理念・社会性を重視して発信したい
・家族の同意や周囲の理解が重要な業種(医療・介護など)
Facebookは、若年層よりも中堅〜ベテラン層への採用アプローチや、企業としての安心感・誠実さを伝えたい企業にとって、有効なチャネルとなります。
YouTube:動画で深く伝える企業の魅力
・職場の雰囲気や研修の様子などをリアルに発信
・入社後を具体的にイメージしてもらいやすい
・SEOにも強く、長期的な資産になる
YouTubeは、長尺の動画で企業の魅力を丁寧に伝えられるプラットフォームです。職場の様子や社員インタビュー、研修の様子、現場密着などを動画で紹介することで、求職者は入社後の具体的なイメージを持ちやすくなります。
特にBtoB業界や専門性の高い業務内容を扱う企業においては、静止画や短文では伝わりづらい部分を補完できる点が強みです。また、求職者の関心が高い「リアルな働き方」や「社員の人となり」を映像で見せることで、企業理解と信頼感を高めることができます。
・YouTube自体が“検索エンジン”として機能
・企業名・職種名での自然検索流入に期待
・タイトル・タグ設計でリーチ拡大も可能
動画はSEOにも強く、YouTube自体が検索エンジンとして機能しているため、企業名や職種に関するキーワードでの流入も期待できます。さらに、動画をInstagramやTwitterなど他のSNSと連携させることで、コンテンツの資産価値を最大化することも可能です。
✅ こんな企業におすすめ
・BtoB・製造・専門職など“体感”が大事な業界
・社風や働き方を「映像」で伝えたい企業
・コンテンツを中長期の採用資産にしたい場合
YouTubeは、情報量をしっかり届けたい企業や、社内の雰囲気を映像で可視化したい場合に特に適した媒体です。
TikTok:若年層へのカジュアルな訴求
・縦型・短尺動画で軽快に情報を発信
・Z世代にリーチしやすく、親しみやすさが魅力
・トレンドやBGMを活かした演出で拡散力抜群
TikTokは、短尺の縦型動画を中心としたSNSで、特に10〜20代のZ世代ユーザーに高い人気を誇ります。リズム感のあるBGMやトレンド要素を活かした動画で、企業の日常や社員の素顔を軽やかに発信できる点が特徴です。
採用活動においては、職場の一日を紹介するVlog風動画や、社員によるチャレンジ動画、ユニークな制度紹介などが効果的です。応募のハードルを下げたいとき、カジュアルな雰囲気で企業に親しみを持ってもらいたいときに特に有効です。
TikTokのアルゴリズムは、フォロワー以外にも動画を届けやすい「おすすめ表示」機能が特徴。
話題性のあるコンテンツが一気にバズることも。
また、TikTokのアルゴリズムは「おすすめ」への表示によってフォロワー以外にも動画が届きやすく、拡散力に優れている点も魅力です。企業アカウントが話題になることで、一気に認知が広がる可能性もあります。
ただし、軽快さや親しみやすさが求められるため、他SNS以上にクリエイティブ性が必要になります。企画設計や投稿頻度を保つための体制づくりも重要です。
✅ こんなときに活用
・Z世代に最初の接点をつくりたい
・企業イメージを柔らかく見せたい
・採用のハードルを下げて間口を広げたい
TikTokは、若年層への第一印象づくりや、採用ブランディングの初期接点として有効なチャネルです。
LINE:1対1のコミュニケーションで応募促進
・国内トップクラスの利用率
・応募者との1対1の対話に強い
・リマインド・日程調整・自動応答にも対応
LINEは、日本国内で圧倒的な普及率を誇るメッセージアプリであり、採用活動においては「応募者との個別対応」に強みを発揮します。LINE公式アカウントを使えば、求職者への情報発信や問い合わせ対応、面接日程の調整などを手軽に行うことができます。
・LINEは“日常的な連絡手段”
・メールや電話よりも開封率・返信率が高い
・返信の心理的ハードルが低く、離脱を防ぎやすい
メールや電話に比べ、LINEは開封率・応答率が高く、特に若年層にとっては“もっとも気軽に使える連絡手段”です。企業側にとっても、チャットボット機能や自動応答の設定により、効率的な運用が可能です。
また、エントリーフォームのURLを送ったり、説明会や面接前日にリマインドメッセージを送ったりと、応募率や参加率の向上にも寄与します。採用だけでなく、内定者フォローや入社後のオンボーディングにも活用できるのが特長です。
LINEは拡散や認知向上には不向き。
「応募者との接点・関係構築」に特化したチャネルとして活用を。
ただし、LINEはクローズドな媒体であるため、ブランディングや拡散には向きません。あくまで「応募者対応に特化した導線」として設計するのが効果的です。
SNS採用を成功させる3つのポイント
手軽に始められる反面、「やってみたけどうまくいかない」ケースも。
成果を上げるには“基本戦略”が重要です。
SNS採用は手軽に始められる反面、「やってみたけどうまくいかない」というケースも少なくありません。成果を上げるためには、ターゲット設定・コンテンツ設計・運用体制といった基本戦略が不可欠です。
「誰に向けて発信するのか」を明確にすることで、訴求力が格段にアップ。
求職者が気になるのは“仕事内容”より“人や雰囲気”。共感される内容に。
投稿の「継続」が信用を生む。更新が止まらない運用体制づくりがカギ。
ここでは、SNS採用を成功に導くために企業が押さえておくべき3つのポイントを解説します。どれも特別なスキルは不要ですが、採用戦略にSNSを本格的に取り入れるには、明確な狙いと地道な取り組みが求められます。
次のセクションでは、それぞれのポイントを具体的に掘り下げていきます。
ターゲットを明確にしてペルソナを作成する
ペルソナが明確になると、
投稿の言葉・テーマ・トーンに“ぶれ”がなくなります。
SNS採用で成果を上げるには、「誰に向けて発信するのか」を明確にすることが不可欠です。年齢・性別・職種・価値観・SNSの利用傾向などをもとに、具体的な求職者像=ペルソナを設定することで、発信内容に一貫性が生まれます。
・都内在住の大学3年生。SNSで企業研究中。
・20代前半の転職希望者。やりがい重視・成長志向。
→ 使う言葉やビジュアル、投稿時間も変わってくる!
たとえば、「都内在住の大学3年生で、SNSを活用して企業研究をしている」「20代前半の転職希望者で、やりがい重視・成長志向」といったペルソナを想定することで、使う言葉や投稿のトーン、コンテンツのテーマが絞り込みやすくなります。
ペルソナ設計をせずに情報を発信すると、「誰にも響かない採用広報」になりがちです。まずは採用したい人物像を具体的に描き、それに基づいた企画設計を行うことが、SNS採用成功への第一歩です。
情報発信の目的に合わせたコンテンツを企画する
「フォロワーを増やしたい」ではなく、
「誰に・何を・何のために伝えるか」を明確に。
SNS採用では「何を伝えるか」が成果を左右します。フォロワー数やエンゲージメントを目的にするのではなく、企業の採用課題に合わせて、届けたい内容とその目的を明確にすることが重要です。
・企業理解を深めたい → 社員インタビュー/オフィス紹介/1日の密着動画
・応募数を増やしたい → 募集要項の詳細/選考フローの案内/Q&A
たとえば、「企業理解を深めてミスマッチを防ぎたい」のであれば、社員インタビューやオフィス紹介、1日の仕事密着などが有効です。「応募数を増やしたい」場合は、募集要項や選考フローを丁寧に解説した投稿が適しています。
また、各SNSの特性に合わせてコンテンツを最適化することも大切です。Instagramではビジュアル重視の投稿、TikTokでは軽快で親しみやすい動画、X(旧Twitter)では速報性や日常の小ネタが効果的です。
✅ 成功の鍵
目的 × ペルソナ × SNSの特性
この3軸でコンテンツを組み立てれば、
求職者の心に届く投稿が自然と生まれます。
目的に合わせて、誰に・何を・どう伝えるかを設計したコンテンツは、確実に求職者の心に届きます。
継続的に発信する
SNSは短期施策ではなく、中長期で信頼と共感を育てる手段。
更新の有無は企業姿勢そのものを映します。
SNS採用は「一度投稿して終わり」では効果が出にくい施策です。認知から共感、応募、入社までの一連の流れをつくるには、継続的な情報発信が必要です。
特にZ世代は、企業の投稿頻度や内容の一貫性を敏感に見ています。「何ヶ月も更新されていないアカウント」は、企業姿勢そのものへの不信感につながることもあります。逆に、定期的な発信を行っている企業は、活動の透明性や信頼性を高めることができます。
・月ごとの投稿テーマを決める
・社員参加型の投稿体制にする
・テンプレートやフォーマットで投稿負荷を軽減
継続のためには、投稿スケジュールの策定や、ネタ出し・担当分担といった運用体制の整備が不可欠です。月単位でテーマを決める、社員を巻き込む、簡単なテンプレートを用意するなど、負荷を分散する仕組みも有効です。
✅ POINT
SNS採用は“続ける力”が成果に直結します。
無理なく続けられる仕組みづくりが、採用力強化への鍵となります。
SNS活用のメリット・デメリット
SNSは柔軟かつ影響力のある採用手法ですが、
特有のリスクも伴います。両面の理解がカギです。
SNS採用は、ターゲットに合わせて企業の魅力を発信できる柔軟性の高い手法です。一方で、運用における注意点も多く、導入にあたってはメリットとデメリットの両面を理解しておくことが重要です。
ここでは、企業がSNS採用を取り入れる際に知っておくべき代表的なメリットとデメリットを整理し、それぞれに対する対応策や活かし方を解説します。
✅ SNS採用のメリット
- 低コストで広範囲にアプローチ可能
- 企業文化・雰囲気をリアルに伝えられる
- ターゲットに合わせた情報発信が可能
- ブランディングと採用の両立ができる
- 動画・画像など多彩な表現ができる
⚠ SNS採用のデメリット
- 炎上リスクがある
- コンテンツ運用に手間と時間がかかる
- 短期的な効果は出づらい
- 継続しないと信頼を失う可能性
- 社内理解や体制づくりが必要
メリット
・投稿・アカウント運用は無料で始められる
・広告運用も少額から可能で、費用対効果が高い
SNS採用の最大のメリットは、コストを抑えながら広範囲に情報を届けられる点です。求人媒体と違い、SNSは基本的に無料で活用でき、有料広告を使う場合でも少額からスタートできるため、費用対効果に優れています。
・社員の雰囲気や職場の空気感が伝わる
・動画・写真でイメージを共有しやすい
・求職者の不安解消にも効果的
また、企業のリアルな姿を発信できることも強みです。社員の雰囲気や職場の空気感、仕事のやりがいなどを写真や動画で伝えることで、ミスマッチのない応募を集めやすくなります。
・1つの投稿が大きく広がる可能性あり
・ハッシュタグやトレンドの活用で認知拡大も
さらに、SNSの投稿は拡散性が高く、1つの投稿が思わぬ広がりを見せることもあります。ハッシュタグやトレンドに乗せた企画は、認知度の向上にもつながります。
・今すぐ応募しない層とも接点を持ち続けられる
・「採用している会社」という認知を定着させやすい
定期的な発信により「採用している会社」という認識を継続的に持ってもらえるため、今すぐ応募しない層への長期的なアプローチにも効果的です。
デメリット
・投稿やコメント対応の失敗が企業イメージの損失に直結
・トラブル対応マニュアルやガイドラインの整備が必要
SNS採用には多くの利点がありますが、注意すべきデメリットも存在します。まず挙げられるのが「炎上リスク」です。不適切な投稿やコメント対応を誤ると、企業イメージの毀損につながる恐れがあります。
・投稿企画・撮影・編集・配信・反応対応などが必要
・継続的な発信体制を整えなければ逆効果に
また、SNSの運用には時間と労力がかかります。投稿の企画・撮影・編集・配信、さらにはコメント対応など、定期的な発信体制を整えなければ“放置されたアカウント”として逆効果になる可能性もあります。
・初期はフォロワーが少なくリーチが限定的
・短期的な成果を求めすぎると挫折につながる
さらに、SNS採用は即効性があるとは限りません。フォロワーが少ない初期段階では投稿のリーチも限定的で、結果が出るまでに時間がかかるケースがほとんどです。短期的な成果を期待しすぎると、途中で挫折してしまうこともあります。
・リスク管理:投稿ルール/緊急時の対応策を明文化
・体制づくり:投稿役割・スケジュール管理を明確化
・視点:短期でなく中長期目線で成果を評価
これらのデメリットに対応するには、運用体制の整備・リスク管理・中長期での視点が欠かせません。
まとめ:具体的な事例から効果的なSNS採用を学ぶ
成功の鍵は、目的・ターゲット・戦略の明確化と
継続的な運用体制です。
SNS採用は、求職者との距離を縮め、企業の魅力をダイレクトに伝えることができる、現代における有効な採用手法の一つです。InstagramやTikTokなどを活用すれば、職場の雰囲気や社員の人柄といった“働くリアル”を可視化でき、Z世代を中心とした若年層に自然なかたちでアプローチできます。
一方で、効果を出すには戦略的な運用が不可欠です。ペルソナ設計や投稿設計、継続的な発信体制、そして炎上リスクを避けるためのルール整備など、計画性を持って取り組むことが求められます。
・自社に合ったプラットフォーム選定
・ターゲットと目的を明確に
・ブランディングと採用を同時に強化
自社に合ったプラットフォームを選び、ターゲットと目的に応じた発信を積み重ねていくことで、採用効率の向上だけでなく、企業ブランディングにも好影響を与えることができます。
すでに多くの企業が実践し成果を上げている今こそ、事例に学びながら、貴社でもSNS採用を本格的に取り入れるタイミングではないでしょうか。

求人・採用にまつわることなら何でもご相談ください
アド・イーグルってなんの会社?
株式会社アド・イーグルは、株式会社リクルートホールディングスのトップパートナーとして様々なメディアを取り扱っている総合広告代理店です。リクナビNEXT・タウンワークなどの求人メディアやAirワークなどの企業HPのサービスやindeedなどの求人情報検索サイトを活用して各企業の課題に合わせた採用活動を提案・支援しています。