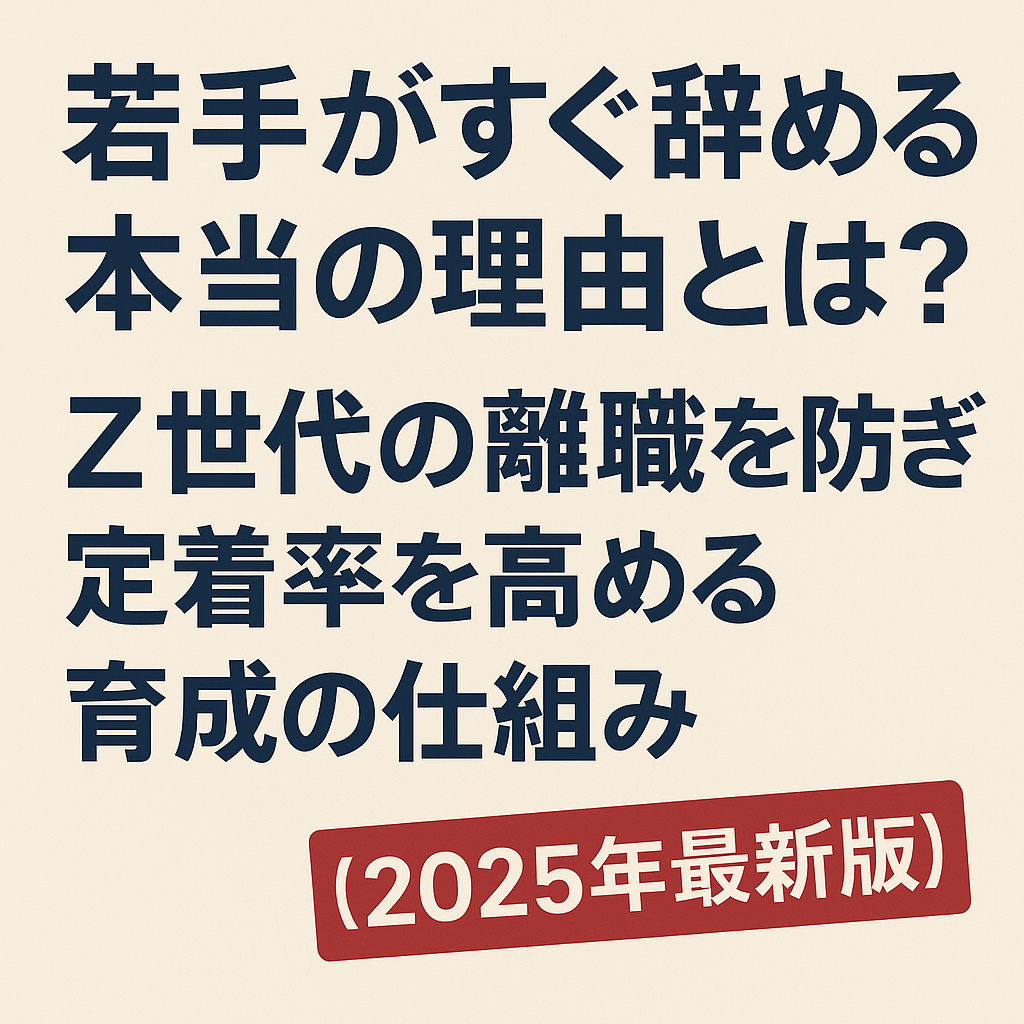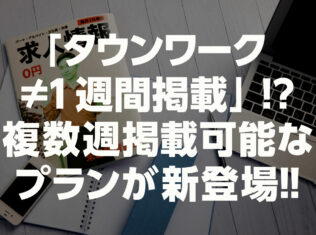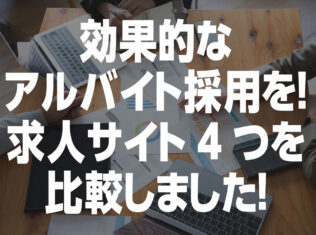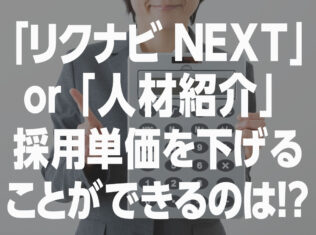目次
若手がすぐ辞める本当の理由とは?Z世代の離職を防ぎ定着率を高める育成の仕組み【2025年最新版】
「丹精込めて育てても、若手がすぐに辞めてしまう…」
採用や育成の現場で、こうした悲痛な叫びを耳にすることが日に日に増えています。コストをかけて採用し、時間をかけて指導した人材が去っていくのは、担当者にとって大きな精神的負担であり、組織にとっても深刻な損失です。
でも、少しだけ立ち止まって、ご自身の新人時代を思い出してみてください。何にワクワクし、どんな言葉に傷つき、どういう瞬間に「この会社、合わないかもしれない」と感じたか。実は、現代の若者が抱える感情も、その根本は同じです。ただ、彼らは私たちよりも「会社を辞める」という選択肢が、はるかに身近になった時代に生きているに過ぎません。
この記事を書いている人
林 賢志
これまで1000社以上のクライアントに対し、Indeed運用を含む採用コンサルティングを提供。新人の育成担当から、10名程度の営業組織のマネジメントを経験。
私自身、マネージャー時代に「見て学べ」という古い価値観で指導を行い、期待していた若手を数ヶ月で離職させてしまった苦い経験があります。良かれと思ったことが、彼らの成長意欲を奪っていたのです。その失敗から、育成は「指導」ではなく「設計」であると痛感し、個々の価値観に寄り添う仕組み作りに注力してきました。
結論を申し上げます。人材育成に「唯一の正解」はありません。しかし、若手が育ち、辞めないための「仕組み」と「環境」は、企業の意思で確実に作れます。
本記事では、1000社以上の採用支援実績と公的データに基づき、若手社員、特にZ世代の離職要因を企業側の視点から構造的に分析します。そして、明日から実践できる育成環境の整え方や、具体的な職場改善のヒントを豊富にご紹介します。
1. 若手社員の離職はなぜ止まらないのか? データで見る深刻な実態
1-1. 【2025年最新データ】大卒の約3人に1人が3年以内に辞めている現実
採用面接で「成長できる環境です」と魅力的に語りながら、入社後は研修も育成計画もないまま現場に放置する──。そんな環境で若手の離職が起きるのは、もはや必然と言えるかもしれません。この問題を裏付けるように、厚生労働省が公表した最新データは衝撃的な事実を示しています。
長年定着している「すぐ辞める若手」という言葉。しかし、その原因は本当に若者側にあるのでしょうか? 私は、その大半が企業側の準備不足、すなわち“育成できる環境が設計されていない”ことにあると考えています。
1-2. 離職理由の根っこは「成長実感の欠如」と「人間関係」
内閣府の調査(令和4年版 子供・若者白書)によると、若者が最初に就職した会社を辞めた理由の上位には、「仕事が自分に合わなかった」「人間関係がよくなかった」が並びます。特に「仕事が合わない」という理由は、「やりたい仕事じゃなかった」という単純なワガママではありません。むしろ、「この仕事を通じてどう成長できるのか」「自分の未来にどう繋がるのか」という道筋を会社側が示せなかった結果と捉えるべきです。
2. 「育成」が機能しない組織の“負”の共通点
2-1. OJTが「現場に丸投げ」の実態
OJT(On-the-Job Training)は、本来「職場内での計画的・段階的な育成手法」を指します。しかし、多くの現場ではその意味が形骸化し、「あとは現場でよろしく」という“放任育成”の隠れ蓑になっています。
これは言わば、レシピも調理器具の使い方も教えずに「今日からこのキッチンを任せたよ」と言っているようなものです。これでは美味しい料理が作れるはずもありません。
2-2. 「背中を見て学べ」では、もう何も伝わらない
「俺たちの若い頃は、先輩の技術を見て盗んだものだ」──この言葉は、もはや育成の放棄を意味する“思考停止ワード”です。Z世代は、生まれた時から情報が整理された環境で育っており、暗黙知や非言語的なニュアンスを察することを極端に苦手とします。そもそも、業務経験のない若手に「背中を見ろ」と伝えても、「何を見て、何を、どのように学べば良いのか」という観察のポイントが分かりません。
3. 「分かったつもり」が定着率を蝕む
3-1. “わかったふり”を生む職場の空気
若手社員が「はい、分かりました!」と元気よく返事をしても、本当に理解しているとは限りません。「こんなことも分からないのかと思われたくない」「質問して相手の時間を奪うのが申し訳ない」といったプレッシャーから、その場をやり過ごすために“できたふり”をしてしまうのです。「この前説明したよね?」という言葉が飛び交う職場は、すでに危険信号。それは心理的安全性(※組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態)が欠如している証拠です。
3-2. フィードバックのない現場は“空気”が支配する
明確なフィードバックがないと、若手は「何が良くて、何が悪いのか」を判断できず、次第に「怒られないこと」を最優先に行動し始めます。これは健全な成長を妨げる最大の敵。学びよりも“空気を読むこと”にリソースを割くようになり、自発的な行動や改善意欲は生まれません。
4. 育成は“指導”ではなく“設計”である
4-1. 属人化した「いい先輩頼み」からの卒業
「○○さんの下に付けば伸びるけど、△△さんだと辞めてしまう」──そんな声が聞こえる職場は、育成を個人の資質や相性に委ねている証拠です。これでは運任せのルーレット育成と何ら変わりません。誰が指導担当になっても一定の質を担保できる共通の「育成の設計図」が必要です。
4-2. オンボーディングプランという「育成の設計図」を作る
育成とは、場当たり的な指導ではなく、事前に「どう育てるか」を計画する営みです。例えば、以下のようなオンボーディングプラン(※入社後の定着・戦力化計画)を明文化するだけでも、属人性は大幅に排除されます。
【オンボーディングプランの簡易サンプル】
- 入社1週目:目標「会社の雰囲気に慣れ、チームメンバーと顔と名前が一致する」。実施項目「社内システムの使い方レクチャー」「チーム全員との1on1(15分自己紹介)」
- 入社1ヶ月目:目標「OJT担当者の同席のもと、簡単な定型業務を一人で完遂できる」。実施項目「週次での振り返り面談(KPT法など)」「業務マニュアルの読み合わせ」
- 入社3ヶ月目:目標「担当業務の独り立ち。自分で改善点を見つけられる」。実施項目「人事部とのフォローアップ面談」「次の半年間の目標設定」
いつ、何を、誰が教えるのか。どのタイミングで評価・振り返りを行うのか。これらを構造化することで、若手は安心して成長のステップを登っていくことができます。
5. まとめ|若手が辞めない職場づくりの第一歩
Z世代は、“指示待ち”ではなく“対話待ち”の世代です。「言われたことをやる」のではなく、「一緒に考えてくれる人」にこそ、彼らは心を開きます。人材育成に絶対の正解はありません。しかし、「向き合い続ける姿勢」こそが、最高の育成策だと私たちは信じています。
🎯 ポイント再確認
- 若手の早期離職は“本人の問題”ではなく、“企業の設計不足”が主な原因。
- Z世代は“成長の納得感”と“心理的安全性”を何よりも重視する。
- 育成は指導や根性論ではなく、計画的な「設計」と「仕組み化」が鍵。
- 制度よりも、日々の対話とフィードバックが定着率を高める。
✅ 明日からできる“行動チェックリスト”
- 週に一度、若手社員と業務以外の雑談をする時間があるか?
- 「ありがとう」「助かったよ」と、成果だけでなくプロセスを承認しているか?
- 失敗を報告された時、「なぜ」ではなく「どうすれば次は防げるか」を一緒に考えているか?
- 「育ててやろう」ではなく「一緒に成長しよう」というスタンスで向き合えているか?
6. よくある質問(Q&A)
Q1:若手社員がすぐ辞めてしまうのは、結局“本人の甘え”ではないのですか?
A1:表面的にはそう見えるかもしれません。しかし、裏を返せば“働く意味”や“存在意義”を感じにくい組織構造になっているケースが大半です。「ここで頑張りたい」と思えるだけの魅力や成長機会を企業側が提示できていない可能性を先に探るべきです。
Q2:離職率を下げるために、まず何から取り組めばよいですか?
A2:すぐに始められるのは、「入社1〜3ヶ月の定期面談」の仕組み化です。業務の悩み、人間関係、キャリアの不安などを安心して話せる場があるだけで、孤独感は大幅に軽減されます。まずは本音を話してもらう関係構築から始めましょう。
Q3:どんな情報をSNSや採用サイトで発信すべきでしょうか?
A3:Z世代に刺さるのは、加工された美辞麗句よりも、「普段の様子」や「日常の一コマ」といったリアリティです。理念や制度よりも、「どんな人と、どんなふうに働くのか」が伝わるコンテンツ(例:若手社員の一日のVlog、チームのランチ風景など)が効果的です。
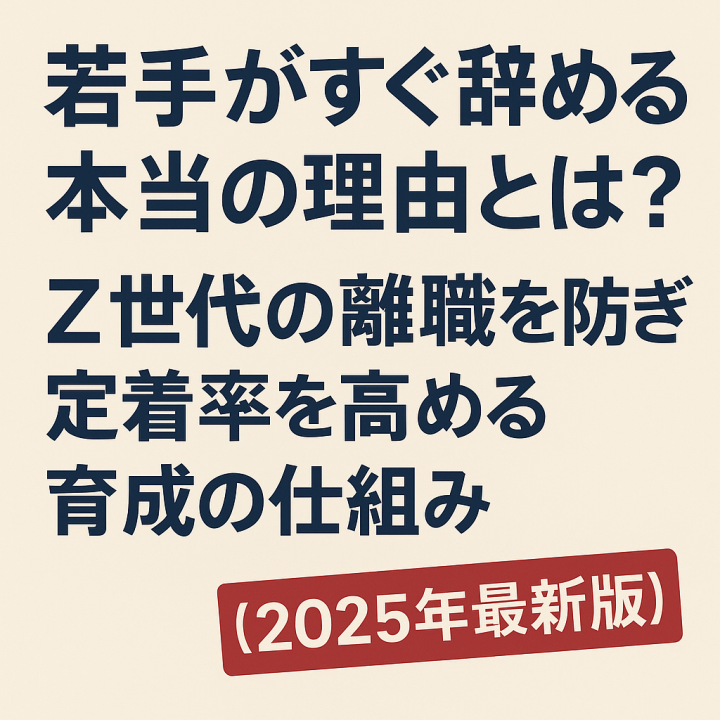
求人・採用にまつわることなら何でもご相談ください
アド・イーグルってなんの会社?
株式会社アド・イーグルは、株式会社リクルートホールディングスのトップパートナーとして様々なメディアを取り扱っている総合広告代理店です。リクナビNEXT・タウンワークなどの求人メディアやAirワークなどの企業HPのサービスやindeedなどの求人情報検索サイトを活用して各企業の課題に合わせた採用活動を提案・支援しています。